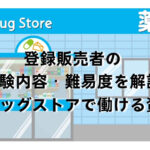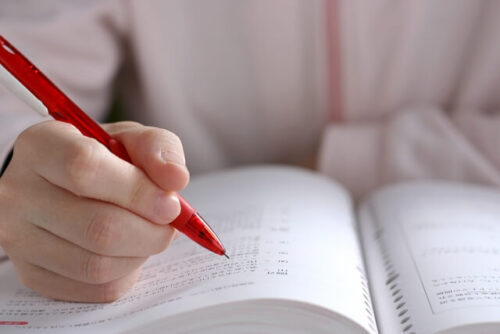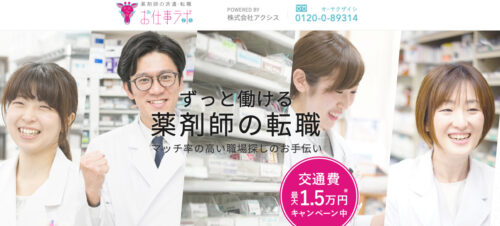【広告を使用しています】
薬剤師は、薬に関する深い知識を持つ専門家です。
この職業は医療分野でのキャリアにおいて非常に有利な資格であり、就職先も多岐にわたります。
この貴重な職業は高い報酬を得ることができますが、それには広範な知識が求められ、日々新たな薬が開発され続けています。
薬剤師を目指す方や薬学部への進学を考えている方々にとって、今後のキャリア形成に役立つ情報となることを願っています。
目次
私が薬剤師になろうと思ったきっかけ
私は高校時代から理系の科目に魅了されており、大学でも理系の学部に進むつもりでした。
しかし、具体的に何を学びたいのかははっきりしておらず、ただ有名な大学に入ることだけを考えていました。
そんな私に、高校の担任の先生は「それではいけない、何を学びたいのかを考えなさい」とアドバイスをくれました。
その時、私の頭に浮かんだのが「薬学部」という選択肢だったのです。
こちらもCHECK
-

登録販売者の試験内容・難易度を解説|ドラッグストアで働ける資格
登録販売者の資格についてご紹介します。登録販売者は、ドラッグストア等で一般医薬品(第一類医薬品を除く)を販売する資格のことです。試験内容、デメリット、勉強方法などを載せています。
続きを見る
薬は私たちの生活に欠かせないものであり、正しい知識を持つことで日常生活に役立てることができます。
また、家族や友人が薬について疑問を持った際には、適切な飲み方を教えることも可能です。
さらに、薬がどのようにして作られるのかに興味を持ち、薬学部を目指すことにしました。
無事に薬学部に合格し、大学で学びましたが、薬学部には多様な進路が存在します。
薬学部の主な進路先
- 研究職
- 公務員
- 病院薬剤師
- ドラッグストア薬剤師
- 調剤薬局の薬剤師
- 教員
最初は、大学院に進学して製薬会社の研究職を目指そうと考えていましたが、国立大学に通っていたため、多くの教授から研究者になるよう勧められ、自然と大学院へ進む道を選んでいました。
しかし、研究職に就いてからは、毎日同じ環境で実験を繰り返す日々が続き、次第にその楽しさを感じられなくなりました。
気づけば、私は接客業の方が自分に合っていると実感するようになったんです。
こうした一連の経験が、今の薬剤師という職業に繋がっているのです。
薬剤師になるための国家試験
各科目に試験があり、合計得点が65%以上で合格となります。
試験科目
- 法律
- 薬に関する知識
- 患者の病態と薬を結び付ける知識や判断を問う問題
試験方法は、マークシート方式です。
ただし、特定の科目で極端に低い点数を取ったり、倫理的に問題があると見なされる回答を繰り返すと、一発で不合格になる可能性があります。
そのため、全体的にバランスの取れた学習が求められます。
私立大学は有利?
私立大学では、国家試験の勉強に対するサポートが国立大学よりも充実しています。
このサポートがあることで、国家試験の合格率を高めることができれば、より多くの学生がその私立大学を選ぶようになるでしょう。
講義で学んだ内容を教科書で再度学ぶよりも、まずは過去の問題を繰り返し解くことで問題の傾向を把握し、間違えた部分を教科書で確認する方法が効果的です。
毎年、過去に出題された内容からの問題が一定数出るため、無駄な勉強をするよりも、確実に成果を上げることができます。
こちらもCHECK
-

ドラッグストア勤務で有利な資格|登録販売者の資格取得までの道のり
登録販売者の資格を取得し、登録販売者としてドラッグストアで勤務していた時の体験談です。仕事内容・資格取得・給料面・休日面・この仕事についてのことを紹介しています。
続きを見る
自分流の勉強法で暗記
国家試験対策の講義では、予備校の講師が多くの早覚えのゴロ合わせを教えてくれます。
これらのゴロ合わせを活用することで、効率的に知識を身につけることができます。
国家試験は人生の大きな分岐点であり、1点でも多く得ることが重要です。
自己採点の際には緊張から手が紫色になるほどのプレッシャーを感じることもありますが、それだけ真剣に取り組んでいる証拠です。
試験に向けては、特定の科目で赤点を取らないように、全体のバランスを考えた準備が必要です。
特に漢方薬や生薬の問題は毎年難易度が高く、出題数も少ないため、捨ててしまう受験生が多いですが、しっかりと対策を講じることが成功への鍵となります。
薬剤師の資格を取得して
正直に言うと、薬剤師免許を取得したからといって、すぐに薬局で調剤や患者への薬の説明を行うのは非常に難しいことです。
まずは、比較的簡単な薬から始めて、患者への説明や病歴の聞き取りを通じて実践を積み重ねていくことで、徐々に現場での対応力を高めていくことが重要です。
さらに、新しい薬が毎年登場し、医療の常識も変わっていくため、常に最新の情報を把握しておかないと、適切な業務を遂行することができません。
したがって、薬剤師としてのキャリアを歩む中で、継続的な学びが欠かせないのです。
保険薬剤師
また、薬局薬剤師の場合ですが、薬剤師になってから「保険薬剤師」としての勉強が必要になります。
保険薬剤師として学ぶこと
- どのように医療行為から点数(患者にとっての負担金額)を計上するか
- 薬代の計算方法
- 調剤する上での処方日数制限
現場で必要とされる知識は、大学では学ぶことができない重要なものであり、その知識に基づいて業務を遂行することが求められます。
医師に処方内容を確認する際に行う「疑義照会」は、大学で学ぶこともありますが、実際の現場ではより多くの経験を積むことになります。
また、他の医療機関との連携やコミュニケーションは、薬剤師としてだけでなく、一人の社会人としても重要なスキルです。
これらを身につけることが、より良い医療を提供するために不可欠です。
管理薬剤師
そして薬剤師になってから数年経過すると管理薬剤師に任命されると思います。
管理薬剤師の役割
- 薬局のリーダーとしての状況判断
- 調剤過誤を起こしてしまった際の判断と部下への指示
- 各医療機関との関係構築
- 薬局としての売上増の対策
など幅広い業務を担います。
薬局は医療機関でありながら、ボランティアではなく、利益を追求する民間企業です。
近年、国が求める薬局の方向性は「対人から対物へ」となっており、単に薬を提供するだけでは利益を上げることが難しくなっています。
患者が現在服用している薬や、飲み残している薬、特に副作用に注意が必要な薬について確認し、適切な対応を行うことで、算定可能な点数がいくつか存在します。
国が定める調剤報酬を最大限に活用するためには、患者に対してしっかりとした服薬指導を行い、算定できる点数を確実に取得することが求められます。
この取り組みは、単なる利益追求ではなく、患者が服用する薬の安全性を高めることに繋がります。
このように、薬剤師としてのキャリアを積む中で、現場に即した知識を深め、薬局のリーダーとしての役割を果たすことが重要です。
check!
薬剤師の給料面・休日面・待遇など
給料面
私は調剤併設型ドラッグストアで働いていますが、日本全国のドラッグストアでは初任給が30万円を超えることが一般的です。
6年制の大学で学んだことを考慮すると、他の職種と比べてもかなりの高水準だと思います。
さらに、企業によっては一人暮らしをする場合、月に約5万円の住宅手当が支給されることもあります。
このような手当があれば、家賃の負担が大幅に軽減され、実質的な収入はかなり高くなるでしょう。
休日面
休日の数は企業によって異なりますが、労務管理がしっかりしている企業であれば、週休2日制を確保することが可能です。
雇用形態が不明確な個人薬局に就職する際は、労務が不十分な場合もあるため、休日や給与が不安定になるリスクがあります。
したがって、就職先を選ぶ際には慎重に検討することが重要です。
上場企業や大手チェーンであれば、企業のコンプライアンスがしっかりしているため、より安心して働くことができます。
さらに、就職後に処方箋調剤が全くできない店舗に配属されたり、処方箋の枚数が少ない調剤室しかない企業に入ると、薬剤師としてのスキルがなかなか身につかない可能性があります。
処方箋の枚数がしっかりと確保できる企業であるかどうかは、今後のスキル向上にとって非常に重要な要素です。
こちらもCHECK
薬剤師の仕事をして思うこと
ドラッグストアで働いていると、患者から薬に関するさまざまな質問を受けることがありますが、その中にはどの書籍や添付文書にも載っていない情報がたくさんあります。
そのような場合、もちろんメーカーに問い合わせて確認することもありますが、薬剤師自身が持っている知識を基に答えを推測し、それを患者にわかりやすく説明する能力が求められます。
つまり、明確な答えがない状況でも、適切な回答を導き出すことが薬剤師の重要な役割の一つだと言えます。
薬剤師を目指す人は多くが優秀ですが、勉強して得た知識だけで答えを見つけることしかできない人がいるのは残念です。
答えが見つからない場合でも、自分の頭を使って解決策を見つけることこそが真の賢さだと思います。
さらに、薬局業務では薬の取り扱いに細心の注意を払う必要があります。
「おそらく薬は合っているだろう」という楽観的な考え方は避けるべきです。
医師と同様に、患者の命に関わる仕事であるため、曖昧な考えを排除し、気になることは必ず調査して、確実な情報を患者に提供することが重要です。
薬剤師として働く上で大切なこと
- 本当に間違っていないのか疑って確認する姿勢
- 連携ミスによる過誤にならないよう薬剤師同士の的確な情報共有
- 一つ一つ念入りに
薬剤師は、患者と医師の間に立つ重要な役割を果たしていると感じます。
時にはその立場が板挟みとなり、辛い思いをすることもありますが、患者が医師に聞けなかったことや伝えられなかったことを薬剤師がサポートし、医師に疑問を投げかけることで、医療の質を向上させることができるのです。
薬剤師であるからといって、必ずしも女性にモテるわけではありませんし、医師と患者の間で苦労することもあります。
しかし、患者の安全を守ることができた瞬間には、大きなやりがいを感じます。
超高齢化社会において、医療従事者が求められる今、ぜひ薬剤師を目指してみてはいかがでしょうか。